世界でトップシェアを誇る自動車用アルミホイールメーカーであるエンケイ株式会社。その商社機能を担う会社として1970年に創業したのが鈴興株式会社だ。現在は、自動車用アルミホイールを中心に、工場向けエネルギー燃料、油脂材料、資材品、工業薬品、金属材料、電化製品等を販売。扱う商材の数は1000種を超え、多くの事業者、ひいては私たちの暮らしを陰ながら支えている。100年企業を目指す同社の変遷と今後の展望について、鈴木博彦代表取締役社長に聞いた。


祖父の代から続く会社を100年企業へ
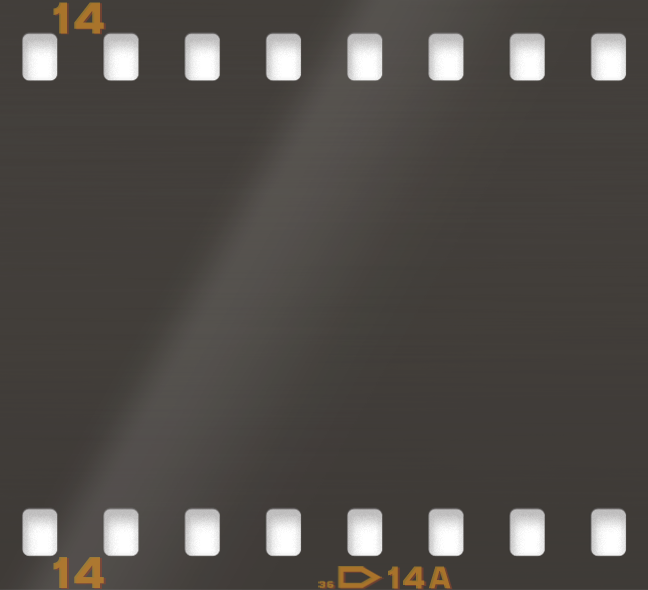

●アルミのスペシャリストの祖父が戦後に起業
鈴興の創業者であり、エンケイの創業者でもある鈴木建次氏は、中島飛行機(現:株式会社SUBARU)で鋳物技師として軍用機の開発・製造に携わっていた。建次氏は持病があったことから戦地へは行かず、友人たちの訃報を受けては、その悲しさと悔しさをバネに仕事に打ち込んだ。しかし、終戦と共に中島飛行機は解散。その後1950年に鋳物技師を集めて、エンケイの前身である遠州軽合金株式会社を創業した。
当初はアルミ鋳造で鍋、釜、湯たんぽなどを製造。目玉となる商品がないことに悩んでいたが、町で売り歩いていた際に転機が訪れる。「偶然通りかかった本田宗一郎さんの目に留まったらしく、アルミ鋳造でのオートバイの内燃部品の製造を持ち掛けられたと聞いています」と博彦氏は言う。それを機にアルミ鋳造と、自動車やオートバイの親和性に気づき、自動車業界でヒットするような商品を模索し続けていた。そんなとき、米国の商社からの依頼でアルミホイールの試作をスタートさせた。「その当時、日本で製造されていたホイールはスチール製が主流でした。アルミ製の軽さと目新しさに驚き、製造への興味を隠せない祖父の姿が目に浮かびますね」と博彦氏はほほ笑む。
●祖父の情熱が日本初のアルミホイールを生む
自社の経験と技術を生かした目玉商品が作れる。そう意気込んだ建次氏だったが、周囲は反発した。「日本での製造実績がないから反対されたのでしょう。しかし、失敗を恐れずに挑戦した祖父の思いが実を結ぶことになります」と話すとおり、1967年に製造とアメリカ向けに輸出を開始。すでに一定のシェアがある中での販売には不安もあったが、日本らしい細やかな技術、綿密な設計、目新しいデザインが評価され、順調な売れ行きを見せた。それが追い風となり、1973年には日本での流通も開始した。
鈴興のアルミホイールの人気に火をつけたのは、あのドラマだった。「1979年から1984年にかけて放送されていた西部警察で、エンケイの製品が使用されたことが大きかったですね。今よりも車を所有することやカスタムすることがステータスだった時代でしたから、象徴的なブランドとして知名度を上げました」。アフターマーケット用品の販売、OEM品のアルミホイール、エンジン部品の製造工程で使用される工業製品全般の販売を行う企業にまで成長を遂げた鈴興は、自動車産業では替えの利かない存在になった。




●すぐに決断できるようにいつも身軽で
そんな歴史を持つエンケイと共に歩み続けた鈴興の4代目代表取締役社長に博彦氏が就任したのは、入社から16年後にあたる2016年のことだった。「中学卒業後、サッカー選手を夢見て、ブラジルに渡りました。ですから、家業を継ぐということは夢にも思っていませんでしたね」と笑う。しかし、目を怪我したことから、プロになることを断念。先代でもある父親に声を掛けられたことで入社したという経緯があった。
代表取締役社長といえば企業のリーダーだが、社員に対してはこれまで通りフラットに接した。「自分が特別優れているという気持ちは一切なく、むしろ社内で一番能力が低いと思っています。ですから、上からものを言う気にはなれませんし、社員を信用するしかありません」と話す。顧客と話をしたり、現場を見たりする機会は社員の方が圧倒的に多く、口を出すと返って邪魔になることもあると感じている博彦氏。「究極的に言ってしまえば、社長の仕事というのは大きな決断と責任をとるくらいです。ですから、社員に求められたら、すぐに決断できるよう、常に身軽でいる必要があります」と語る。
今、鈴興が目指しているのは100年企業になることだ。そのために行ってきた大きな取り組みが二つある。一つは人事マネジメントだ。事業を継続するうえでは、若い世代で基礎を固める必要があった。しかし、社内を見渡せば5、60代の社員ばかり。博彦氏は、若くして入社し、さまざまな部署での経験を通じて養った目で、新陳代謝を図っている。
もう一つが認知度の向上だ。エンケイが近隣では一目置かれる存在であるため、パートナー企業として、鈴興の認知度も同じように上げていかなければいけないという。「存在を知ってもらわないと、若い世代に入社してもらえませんし、ビジネスパートナーとして選ばれることもないでしょう」と語る。
そこでブログとSNSの運用を開始。「読者やフォロワーから反応を得られると、社員の中でいい意味での自意識が高まり、一段と結束力が高まったように感じます」という予想外の副産物もあった。「どれだけ素晴らしい事業でも、継続をしなければ社会に貢献し続けることはできません。これからも会社と社員の雇用を守ることを大切にしたいですね」と展望を描いた。
![[●REC]](https://rec.weekly-economist.com/wp/wp-content/themes/rec/img/logo_b.png)
